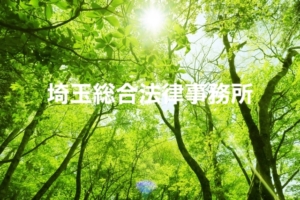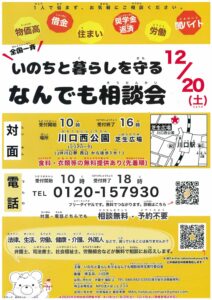最近、自身あるいは自身が経営する事業がインターネット上で他人の投稿により誹謗中傷を受けているとの相談が寄せられています。この場合、まずその投稿が削除できるかを考えます。取扱いはサイトにより異なりますが、削除依頼受付のメールフォームがあるサイトであればそこから自身で削除依頼をすることになります。
それで削除できなければ、弁護士に依頼してサイト管理者に通知書を送付したり、削除仮処分の裁判を起こすことを検討します。
このほか、投稿者を特定して損害賠償請求をすることも考えられます。
この場合、発信者情報開示申立の裁判により、投稿者が契約しているプロバイダの情報を得て、そこから投稿者の氏名、住所等を開示してもらい、投稿者に対して請求していくことになります。
裁判では、削除、開示いずれの場合も名誉毀損の成立のために具体的な事実の指摘に基づく社会的評価の低下が必要となります。このハードルが決して低くはなく、例えば「金目当て」「最悪」「最低」といった投稿でも、具体的事実の指摘ではなく投稿者の不満や感想を述べたに過ぎないとして名誉毀損が認められないことがあります。
名誉毀損の判断は難しいこともありますので、お困りの際は弁護士にご相談ください。
(事務所ニュース・2024年新年号掲載)