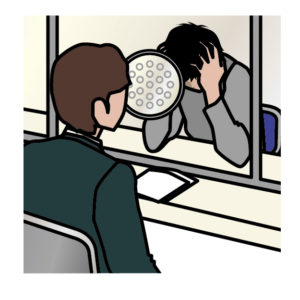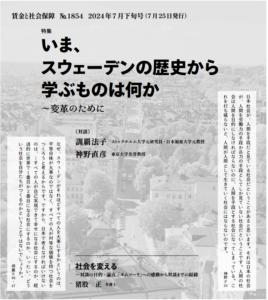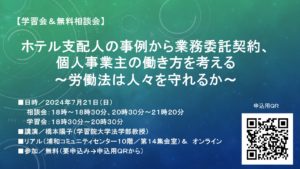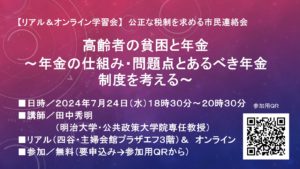現在、我が国では、国政選挙に立候補する場合、衆議院・参議院いずれも選挙区で300万円、比例区で600万円という高額の供託金を納めなければならず、しかも、得票数が一定以下の場合には没収される制度になっています。埼玉県在住のA氏は、平成26年12月に行われた衆議院小選挙区選挙に立候補しようと思い、立候補に必要な各種書類を揃え、提出したものの、小選挙区の立候補に必要な300万円の供託金を用意することができなかったため、同選挙に立候補することができませんでした。そこで、選挙供託金違憲訴訟弁護団を結成して、私もこれに参加し、同制度を定めた公職選挙法の規定が立候補の自由を保障する憲法15条1項等に違反する憲法違反の規定であるとして、国を被告とし、平成28年5月に東京地方裁判所に提訴しました。
我が国の選挙供託金制度は、大正14年に男子普通選挙制が実施された時から始まります。この制度が導入された表向きの理由は、売名候補者又は泡沫候補者の立候補を防ぎ、選挙の混乱を少なくし、併せて選挙が誠実厳正に行われる点にあるとされていました。しかし、実際は、無産政党(無産者)の議会への進出を抑制することに真の目的がありました。
実は、供託金制度は世界的に見ると当然のものではありません。OECD加盟国35カ国(調査当時)中23カ国では供託金制度が存在せず、供託金が存在する残り12カ国でも、イギリス下院は約7万円、オーストラリア下院は約8万円であり、日本の300万円や600万円という金額は突出して高額なのです。
また、周知のとおり、我が国の貧困と格差の広がりは深刻で、このような現状を考えれば、選挙区300万円、比例区600万円という選挙供託金制度は、数千万人の国民から立候補の自由という重要な権利を奪う可能性のあるものといえます。
平成28年5月に提訴した本裁判ですが、約3年の裁判を経て東京地裁、東京高裁と続けて敗訴判決(供託金制度を合憲とする判決)が下されました。そこで、弁護団は最高裁に上告をしていましたが、昨年12月に上告棄却決定が下され本裁判は終了しました。裁判自体は終わってしまいましたが、この裁判を通じて供託金に限らず、我が国の選挙制度に様々な問題点があることが分かりましたので、引き続き選挙制度改善に関わっていけたらと思います。
(事務所ニュース・2021年夏号掲載)