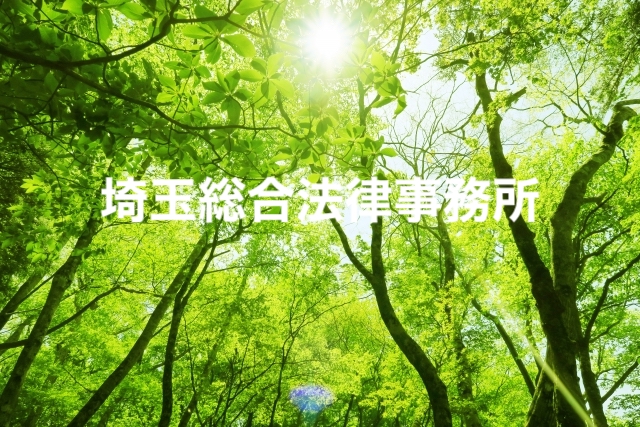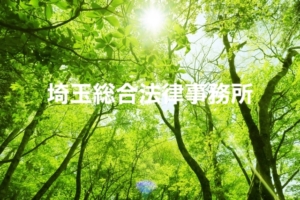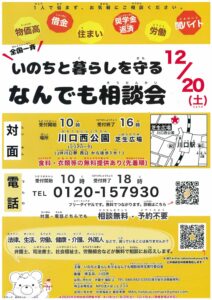数年前から、学校や企業などで、多様性を受け入れる社会の実現を行動指針として掲げるものが多くなり、多様な価値観が反映され始めているような雰囲気もあります。一方で、多様性社会の実現には程遠いと感じる方もいるかと思います。このように、多様性社会の実現が進みにくい原因には、種々のものがありますが、哲学上の議論として、古くから「寛容のパラドクス」が指摘されています。
寛容性や多様性の実現を突き詰めれば、たとえ「寛容性を認めない・多様性を認めない」という価値観であっても、一つの価値観であるとして、社会から排除されるべきではないことになります。一方で、寛容性や多様性を認めないとする価値観は、寛容性や多様性を実現するという価値観を排除しようとするため、結果的に、寛容性や多様性を実現する社会を目指したことにより、寛容性や多様性を認めない社会の実現が達成されてしまうと・・・。
この矛盾をどのように解消するかについては、法哲学上、複数の見解が主張されています。ここでは語り尽くせないので、関心があればお調べいただくとして、今回は、「多様性を受け入れる」という行動に焦点を当てて、取るに足らない個人的な考えを一方的に示して終わりとさせていただければと思います。
多様性を「受け入れる」以上は、どのような価値観も排除すべきではないので、不快・不愉快といった理由で、発言者を攻撃することはできないはず。もっとも、「受け入れる」ことは、無防備・無批判・無関心と同じではないはずなので、何らかの意見について、批判的または肯定的な意見を持つことが推奨されているはず。だとすると、「多様性を受け入れる」ことは、それぞれの価値観の長所も短所も、相互に正しく理解している状態を指すはず。
多様性社会は、様々な価値観を正しく認識するという段階であって、その先には、「多様な価値観を、公正にどう実現するか」という段階(多様性実現社会?)があるので、多様性社会の段階で時間をかけてはいられないとも考えられます。一方で、これまで認識していなかったことを正しく認識するには、相当の時間を要する人もいて、最も衝突が起きやすい段階ということなのでしょう。