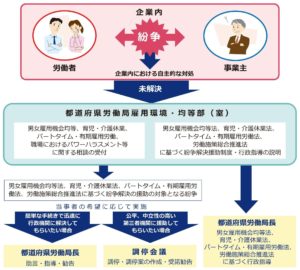弁護士 宮澤 洋夫
* 戦後復興の流れ
広島・長崎に原爆が投下され、それを契機に太平洋戦争は終結された。3月11日、東日本大震災に伴う被害者の規模は、昭和20年8月9日長崎に投下された原子爆弾による被害者数と略々匹敵する規模のものであった。
米軍占領下の復興は被害の甚大、深刻さから遅々として進まなかったが、財閥解体、税財政改革、農地改革等がなされ、憲法改正により我が国は民主国家に改変された。戦争による深刻な被害の回復・経済復興は、昭和25年に勃発した朝鮮戦争の特需が切っ掛けとなった。情勢は警察予備隊の創設に連なり、日米平和条約、安全保障条約締結とで、昭和28年には朝鮮戦争休戦協定が調印された。
昭和29年に入り、第五福竜丸被災事件が発生し、原水爆禁止運動は全国的に盛り上がり、学術会議は原子力研究三原則を声明した。他方、日米艦艇貸与協定が締結され、防衛庁設置法、自衛隊法が公布された。
昭和30年には防衛六ヶ年計画が決定され、その頃から神武景気に入った。第1回原水爆世界大会が開催され(昭和35年8月6日)、日米原子力協定(昭30年2月15日)が成立し、原子力基本法、原子力委員会法(昭和30年12月19日)が公布され、産業政策として原子力開発 開始された。経済白書は「もはや戦後ではない」と宣言している。
*原子力開発の進行
我が国が原子力開発に着手した昭和30年代初期に日本原子力研究所が設置(昭31年6月15日)されて立地決定の翌月には現地事務所を開設し、その3ヶ月後には早くも第1号実験原子炉(JRR-1)の建 設がスタートし、昭和32年8月27日臨界に成功し、日本初の「原子の火」をともした。
昭和20年代後半から昭和30年代にかけて、わが国に産 業界を襲ったエネルギー革命の波は、産業構造を石炭中心から石油中心へと質的転換を遂げさせ、多くの重化学コンビナートを建設してきた。それに伴ない、公害は日本列島にばらまかれて、現在の深刻な様相をもたらした。昭和40年代に至って、政府の産業政策優先と企業の利益優先の姿勢とは相俟ってエネルギー源として新たに原子力利用を実用化し、原子力発電・原子力船建造・放射線利用等産業として急速に確立し、「原子力は将来のエネルギーの有力な担い手として着実にその地歩を進め」てきた。この原子力の実用化・産業化への動向は、企業の経済性の要求により、必然的に安全性の配慮を欠如し、原子力にはつきものの放 射能による産業公害を地域住民にもたらすことが予想される。しかも、巷間に噂される原子力の軍事利用に至るときは、かつての広島・長崎の再現は必至である。原子力公害は1970年代にに新たな問題を提起している。
*最初の原子炉訴訟の勝利
(1)三菱大宮原子炉
日本最初の原子力船「むつ」(8354総トン)は、昭和47年6月の完成を目標に、船体部は石川島播磨重工業が28億9700万円、原子炉は三菱原子力工業が26億7000万円で建造契約が締結された。
「むつ」に使用する原子炉は、途中でアメリカの原子力潜水艦用原子炉メーカーであるウェスチングハウス(W・H)社からの輸入原子炉に変更された。三菱は 「むつ」の動力用原子炉作成の基礎資料を得る目的をもって、昭和41年9月大宮研究所に原子炉(臨界実験装置)を設置する計画を発表した。
さらに、三菱は原子力船開発のための原子炉であって、原子力の平和利用のためであると言明しているが、世界にある100隻以上の原子力船のうち軍艦でないものはサバンナ号(アメリカ)とレーニン号(ソ連)の2隻だけであり、原子力船の特性から合理的利用は潜水艦をおいてなく、かつ三菱はわが国の兵器産業の雄で あって、原子炉の設置は「むつ」をもとに原子力潜水艦のために使用されることは十分推測しうるところである。
(2)原子炉設置許可と住民の反対
原子力施設を設置する場合なによりも重要なことは、その安全性であり、最も重視される点が立地条件である。ところが、三菱の今回の設置場所は一番近い人家 までわずか65メートルのところにあり、有数な交通の激しい道路に面する敷地内であり、かつ住宅・工場等の密集地帯である。
また、三菱は住民に対し昭和34年11月14日、大宮市北袋町の大宮研究所には「原子炉の設置はしない」「核燃料の再処理はしない」と確約していた。
ところが昭和43年7月10日にいたって、三菱の原子炉設置申請は、内閣総理大臣により許可された。
この許可に伴い、三菱は7月18日に原子炉収容建物の建築許可申請を埼玉県知事に提出し許可されるにいたった。
地元住民約2000名は内閣総理大臣の許可に対して異議の申立をするとともに、埼玉県建築審査会に対して、原子炉収容施設の建築確認処分に対する審査請求を申立てたが、前者については棄却、後者については却下の処分がなされた。
(3)住民の訴訟提起
そこで地元住民は、埼玉県建築審議会の審査請求に対する却下決定に対し、建築基準法94条3項に違反するので公開による口頭審査を求める行政訴訟を昭和43年11月17日浦和地方裁判所に提出した。
昭和44年11月17日、浦和地裁は、口頭審査手続きを経ることなく却下した裁決は違法であると地元住民勝訴の判決をした(判時579号24頁以下参照)。
建築審査会はこれを不服として東京高裁に控訴の申立をしたが、昭和47年9月棄却され行政訴訟の勝訴は、破棄した。
他方、昭和44年7月7日地元住民約1600名は、原子力基本法の民主・自主・公開の三原則を徹底的に破壊してきた三菱に対し、原子力公害の予防手段として、「大宮市に原子炉を設置しない」と約束した不作為義務の履行を求め、原子炉の撤去訴訟を浦和地方裁判所に提起した。
ところが訴訟中三菱は「原子炉撤去」を発表したため、和解に入り、昭和49年7月17日、原子炉撤去、立入を認める和解が成立し、住民の全面的勝訴により終結した。
*高度経済成長下の原子力訴訟
(1)本件訴訟の性格
原子力委員会は昭和47年6月1日原子力開発利用長期計画を発表し、昭和55年には3200万キロワット、昭和60年には6000万キロワット、昭和65年には1 億KWの発電計画を具体化し、その後再三計画は手直しされたが、運転中15基試運転中の3基を加えれば出力1000万キロワットを超えている。ところが周 辺住民に対する生活環境を保全し、住民の生活と健康を保護する具体的施策を欠如しているために、各地で原発訴訟が提起されている。
日本原子力発電(株)は昭和41年に我が国最初の原子力発電所として建設した東海1号炉(コルダーホール改良型16万6000キロワット)に次いで、昭和46年12月21日に世界最大級の東海2号炉(沸騰水型軽水炉=BWR110万キロワット)の建設を計画し内閣総理大臣に対し設置許可申請を行った。
東海第二原発訴訟は伊方原発訴訟に続く第2の原発訴訟であるが、沸騰水型軽水炉では発の訴訟である。東海福島第二原発訴訟は続いて提訴されたが同型のものである。
福島県太平洋沿岸一帯の3つの巨大な原子力発電所基地群(計14基)と1つの火力発電所基地(2~4基)の建設は、完成すると日本はおろか、世界にも例を見ない発電所の集中過密立地となる。訴訟は内閣総理大臣の原子炉設置許可処分の適法性を争う行政訴訟であるが、その実体は原子力公害の予防を目的とする差止訴訟である。
(2)国の本案前の申立
福島原発訴訟では国は昭和50年10月15日第1回準備書面により頭初から本案前の申立をした。この段階から国は各地原発訴訟で住民の当事者適格を争う態度となった。
国は住民の原子炉施設の危険性についての主張に対し、「原告ら住民が本訴請求についての法律上の利益を基礎づける事実として指摘したところは、『事故が発生すれば』とか、『放射性物質が漏洩した場合』という単なる仮定の事実を前提に置いた危険一般に尽きるものであり、換言すれば、具体的事実に基づかない、したがって、客観性のない、危ぐ、懸念のたぐいにすぎないものというべきである」と暴論をし窓口論争を挑んだ。
これは周辺住民が訴訟により原子炉施設の安全性を争うことを何としても阻止しようとしたものであった。その論争に6年という歳月を費やした。
しかしながら、原子力船「むつ」の放射能漏れ事故をはじめ、スリーマイル島原発の炉心溶融に至る大事故、さらには原子力発電所関係者のみでなく、地域はもとより周辺諸国にまで深刻かつ広汎な損害を与えているチェルノブイリ原発事故を見れば、国の主張がいかに独りよがりの傲慢なものであり、安全性無視のものであるかは明らかである。福島原発においても、運転開始以来幾多の事故が発生しており、それが大事故に発展しないという保証はまったくないのである。裁判 所は何れも住民に訴えの利益を認めざるを得なかった。
(3)訴訟審理と裁断回避
いうまでもなく訴訟の最大の目的は原子力施設の安全性を問うものであった。そのため審査対象、審査基準、被曝評価、原子炉機器の欠陥、廃棄物、原発集合立地等をめぐり危険性の立証を行うとともに、一審では折りから発生したスリーマイル島原発事故を教訓として原発の安全性を問い、さらに控訴審ではチェルノブイリ原発事故に伴う被害の実態を明らか にした。
しかしながら、裁判所は原発技術の未成熟性に眼を向けることなく、原子炉機器の炉工学的安全性について科学技術的審理を避けた。しばし ば発生する核燃料棒事故(PCI)、圧力バウンダリーの応力腐食割れ(SCC)、圧力容器の脆性破壊、緊急冷却装置(FCCS)の不動作、格納容器の構造等についてはスリーマイル島、チェルノブイリその他の多数の事故からその危険性は明らかになっている。しかも、福島原発は大型化しているがその安全性の実証はなく、かつ集中化しており、事故が発生したときは大事故に連なる危険性があって、従業員、周辺住民への被害が予測されるにもかかわらず、これらについても審理判断を回避した。
福島原発訴訟は、最高裁において原子炉設置許可処分の適法性は確定されたが、その安全性については司法判断が回避されて行政の責任とされ今後の対策に委ねられた。
(4)原発訴訟と国側の対処
原発訴訟を提起して以来、国側は現在の原子炉施設について安全であると強弁していたにもかかわらず、住民の主張、立証その他の問題提起に対し、さらには判決を契機として国側および原子力産業の対応にも変化があらわれた。しかし、「安全神話」は、政官財に蔓延し、その体質に変化は見られず、抜本的対策は論ぜられることなく「東日本大震災」を招来した、「人類が核と共存しうるか」科学技術と法の衝突について、司法はこれを避けてとおるのが、解決に向けて正面から対応するのか、原発訴訟はなお現代の課題を提起している。